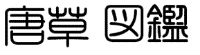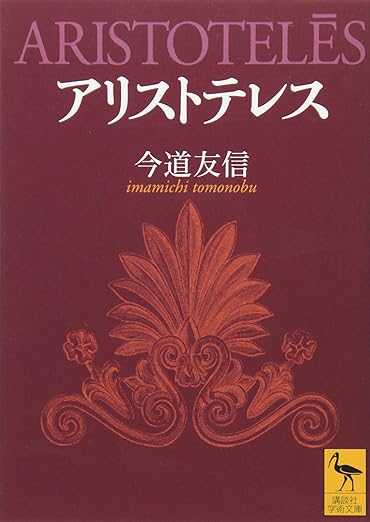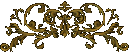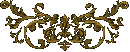芸術史と芸術理論の基礎
芸術理論
![]() 芸術史と芸術理論の基礎を押さえておきたい。プラトンからディドロ、パノフスキー・・、翻訳文献…
芸術史と芸術理論の基礎を押さえておきたい。プラトンからディドロ、パノフスキー・・、翻訳文献…
源流
プラトンPlaton 紀元前427年 - 紀元前347年)
プラトンの思想は西洋哲学の主要な源流であり、哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」という by Wikipedia
プラトンの呪縛 (講談社学術文庫) 佐々木 毅 (著) – 2000/12/8
プラトン全集 - 岩波書店. 田中 美知太郎,藤沢 令夫 編
万学の祖
アリストテレスAristotle前384年 - 前322年3月7日)
「万学の祖」by Wikipedia
最古の建築理論
ウィトルウィクスMarcus Vitruvius Pollio(紀元前80年/70年頃 - 紀元前15年以降)
『建築について』(De Architectura、建築十書)を著した。この書物は現存する最古の建築理論書by Wikipedia
百科全書派
ディドロ(Denis Diderot, 1713年 - 1784年)
18世紀の啓蒙思想時代にあって、ジャン・ル・ロン・ダランベールとともに百科全書を編纂した、いわゆる百科全書派の中心人物で、項目「美」を執筆by Wikipedia
image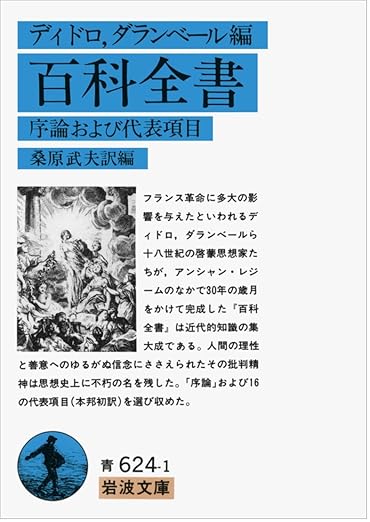
(Amazon)
百科全書: 序論および代表項目
ディドロ (編集), ダランベール (編集), 桑原 武夫 (著) (岩波文庫) 1995
図像解釈学
パノフスキー(Erwin Panofsky, 1892年 - 1968年)
北方ルネサンス研究で知られるほか、彼が理論化をすすめたイコノロジー(図像解釈学)は、20世紀の美術史学にとって「様式論」と並ぶ最も重要な方法論となった by Wikipedia
イデア (平凡社ライブラリー)– 2004 エルヴィン パノフスキー Erwin Panofsky (著)
![]() 上の本であるが、原著1924年刊、訳 2004年 平凡社ライブラリーby伊藤博明、富松保文
上の本であるが、原著1924年刊、訳 2004年 平凡社ライブラリーby伊藤博明、富松保文
分厚いが半分は「註」である。
 中世の部分を中心にこちらで読むことにしますが、その部分、本文12ページ、註釈はその倍の24ページである。(゜_゜)
中世の部分を中心にこちらで読むことにしますが、その部分、本文12ページ、註釈はその倍の24ページである。(゜_゜)
美術史学
美術史(英:Art history)という言葉は、
(1) 絵画・建築・彫刻・工芸品など造型芸術の歴史、
(2) それを研究する学問、の二つの意味で用いられる。
後者は美術史学ともいうby Wikipedia:美術史
16世紀以前 - 旅行記と「列伝」
広い意味での美術史的記述は古代から存在していた。パウサニアスの『ギリシア案内記』のような旅行記・案内記と、大プリニウス『博物誌』に現れるような芸術家・作品についての記録がそれ。
ヴァザーリの『芸術家列伝(画家・彫刻家・建築家列伝)』 (1550)
by Wikipedia:美術史
18世紀〜19世紀後半 -鑑定技術の進歩とイコノグラフィ
ヴィンケルマン『ギリシア芸術模倣論』(1755)
モレッリ『イタリア絵画の芸術批判的研究』(1890-93)
20世紀前半 - 様式論とイコノロジー
アロイス・リーグルは『末期ローマの美術工芸』 (1901) において、広範な地域と時代におよぶ装飾モチーフの分類法と発展の法則を示した。この様式論はヴェルフリンによって理論化がすすめられた。『美術史の基礎概念』(1915)
ヴァールブルクとパノフスキー
ヴェルフリンらが代表する様式論は、美術作品を形態や表現形式といった外形を通じて分析しようとしていたが、新しいイコノロジーは、作品の主題や意味そのものに注目する。図像を象徴的価値をはらむものとして捉え、作品を生んだ文化全体に照らし合わせて作品の意味を解読しようとするイコノロジーは、20世紀前半の美術史において大きな勢力を形成した。by Wikipedia:美術史
美術史批判と方法論の多様化
伝統的なアカデミズムの理論に沿った絵画や彫刻などの「ハイカルチャー (en: High culture」を中心にしてきたことが批判され、たとえば映画や写真、ビデオといった新しい視覚表現が新たに研究対象に加わったため、「美術史」に代えて、広く視覚的な現象全般を対象にする「視覚文化研究」(Visual Study または en:Visual Culture)という名称も多く用いられるようになった。by Wikipedia:美術史
参考文献
⇒放送大学の学生ならネット配信講義を見るのもよさそう・・ ◆https://www.ouj.ac.jp/
美学・美術: 付・研究論集
ドゥニ・ディドロ (著), 鷲見 洋一, 井田 尚 (監修) – 2013/9/26
美学・美術: 付・研究論集 (ディドロ著作集4)
法政大学出版局(pdf)
『美について考えるために』今道友信[著] 日美学園(2011)
『ディドロとルソー 言語と“時”―十八世紀思想の可能性』小宮 彰[著] 思文閣出版 (2009)
『美学史研究』 淺岡 潔[著] アテネ社 学術書
『ディドロと美の真実』 野口 榮子[著]昭和堂
『絵画を見るディドロ (叢書・ウニベルシタス)』ジャン スタロバンスキーJean Starobinski[著], 小西 嘉幸 (訳)法政大学出版局 (1995)
『フランス絵画史 (講談社学術文庫) 』高階 秀爾[著] ( 講談社 (1990)文庫オリジナル。
学術
必携 世界美術大事典 全6冊(1988-1990) 小学館昭和63年。総項目数7,300。総図版数3,200。末吉 雄二/ 日高 健一郎/望月 一史/森田 義之【編】
世界美術大事典:
1:あーかな
2:かにーさ<
3:しーてぇ
4:ておーふぃ
5:ふーむ
6 :めーわ・索引
西洋編全28巻、別巻(1992-1997)
講座美学
今道 友信 編 再掲あり(2014/06/03)今道 友信 著書(amazon)
講座美学1 美学の歴史,東京大学出版会
:執筆者:今道友信,森谷宇一,佐々木健一,西村清和,福永光司,閔周植,五十嵐一,松尾大,尼ヶ崎彬,趙善美:1984年5月
「中国やギリシアの昔から求められ、今世紀になって全面的に開花しかけた美学の成立と変遷の経過を、又その特質を、東西にわたって概観する。
美学史の大略を知るだけでなく、この学問を通じて人類がどのような問題を考えてきたかが理解できるはずである」
美を考える知的営みの歴史を,西洋と東洋とに分けて辿る.序論―美学とは何か/第I部西洋の美学(概観/古代美学史/中世美学史/近世美学の展望/近代美学の成立/現代の美学) 第II部東洋の美学(中国の芸術哲学/韓国の美学思想/日本の美学思想/イスラームの美学思想) 第III部美学史各論(西洋中世の修辞学/中国の肖像画論/日本の詩論)
講座美学2 美学の主題
執筆者:今道友信,利光功,新田博衞,佐々木健一,藤田一美,細井雄介,増淵宗一,加藤信朗:1984年07月
「東西の美学史において、繰り返し問われてきた根本問題のうち、自然、美、美的経験、芸術、創造、象徴、装飾、型、創造など、美学の基本概念をテーマとして選び、理論的な考察を行う、美学の体系的見方を呈示する・・ 」
美学の体系として重要度が高く,しかも,あらゆる他の哲学的諸学科とも深いかかわりのあるテーマを9つ選択して,一貫した体系的連関のもと,それぞれ独自の視点から論ずる.自然/美/美的経験/芸術/想像/象徴/装飾/かた・かたち・すがた/創造
講座美学3 美学の方法
執筆者:今道友信,金田晉,眞鍋將,篠原資明,戸澤義夫,川野洋,藤田一美,庄野進,吉岡健二郎,山縣熙,谷川渥:1984年10月
「学問は方法である、といわれるほど、美学においても方法は重要である。
現在美学の研究で取られておりかつ将来も実り多き成果を生むと思われる方法を選んでその学問的実質を考察する。方法論への手引きであると同時に、現代の美学の観点から浮き彫りにする。」
現在,美学の研究でとられている方法のいくつかを紹介し,その学問的実質を論じて,読者の思考に供する.美学方法叙説/現象学/解釈学/芸術記号論/分析美学/実験美学/形而上学的方法/社会学的方法/比較美学/構造主義/制作学/カロノロジア
講座美学4 芸術の諸相
執筆者:今道友信,国安洋,橋本典子,徳丸吉彦,森谷宇一,佐藤信夫,佐々木健一,河竹登志夫,西村清和,利光功,神林恒道,井上充夫,多木浩二,浅沼圭司 :1984年12月
「芸術は、人間の自己証示として最も重要な人類普遍の文化現象であり、その救命は、人間の可能性をとう美学によっては極めて本質的な課題である。」
人間の可能性を問う美学にとって,人間の自己証示としての芸術を研究することはその本質的課題である.本巻では,音楽・演劇・美術のほか芸術の諸々のジャンルについての美学的芸術学的研究を行う.
講座美学5 美学の将来
技術の非人間化に抗しての人間性の回復,また一方,芸術と技術の共生の問題など,現代の芸術と美学に課せられた課題は大きい.本巻では,様々な提言に学びつつ,技術社会における美学の新しい方向を見定める.
講座美学5に「基礎的文献表」あり
https://www.dokkyo.ac.jp/library/pdf/path_kaiga.pdf
https://libguides.lib.keio.ac.jp/mit_ktoyama
有料・・ 知識検索サイト『JapanKnowledge』小学館グループの株式会社ネットアドバンス提供ギリシア・ローマ神話事典 マイケル グラント, ジョン ヘイゼル (著), 西田 実 (翻訳) – 大修館書店 (1988)
高津 春繁 岩波書店 (1960)/////
【第56回日本翻訳出版文化賞受賞】
ラルース ギリシア・ローマ神話大事典
ジャン=クロード・ベルフィオール (著), 金光仁三郎 , 小井戸光彦 本田貴久 大木勲 他 (訳) 大修館書店 – 2020/6/23
西洋美学史小田部 胤久
美学への招待 (中公新書)佐々木 健一
岩村 透(いわむら とおる、明治3年(1870) - 大正6年(1917)
児島 喜久雄(こじま きくお、1887(明治20) - 1950(昭和25))
陰里 鉄郎(かげさと てつろう、1931- 2010)