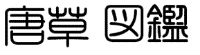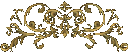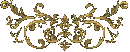十二支の源流
笹間良彦さんの「蛇物語」から十二支の辰と巳の関係は以前(2009年)みてみましたが、それはそうと、獣帯と十二支の関係はどうなのでしょうか?
英語では十二支を Chinese zodiac(中国の獣帯)と呼ぶ。
西洋から見ての話であるが。

『十二支動物の話』
2009年1月購読
あとがきにかえて
==以下引用===========
十二支動物は、前後二つの部分に分けられる。
前半の六つは、穴居に関係したり、拘束される動物である。
後半は穴居に関係なく、拘束されることもない
鼠・兎・蛇は穴居する。
竜は地脈、水脈の中にいる。
牛は洞穴に拘束され、、解放されることによって世界を更新する。
竜蛇は深い穴に潜み、機を見て地上に飛翔する。
前半は地下に関わり、後半は地上に関わる動物であった。
前半は死の世界、後半は再生の世界に属した。
![]() この本、<子丑寅卯辰巳編>とあり、普通に前篇後篇の仕立てだと思って、続きはないのだろうか、両方がそろってから・・と、しっかり読むのを置いて探していた・・
この本、<子丑寅卯辰巳編>とあり、普通に前篇後篇の仕立てだと思って、続きはないのだろうか、両方がそろってから・・と、しっかり読むのを置いて探していた・・
2001中に刊行するというあとがきであったのだが、・・出ていないようだ。
それはともかく、上記の
「前半は地下に関わり、後半は地上に関わる動物であった。」
「前半は死の世界、後半は再生の世界に属した。」というのが、今は結局よくわからない。
今年は巳年であるが、蛇は脱皮するが故に再生の象徴と言われるはずである。(しかし、井本英一さんにはほかに「蛇の伝承と女性」という著書(『習俗の始原を訪ねて』があるという:未読のため後程)・・・以下に続く・・
井本英一『死と再生 ユーラシアの信仰と習俗』をよむ⇒
輪廻転生の世界観
動物転生譚の諸相
十変化の伝承
山の神と野生動物
十干十二支の始原
トーテム獣と十二神
漢訳仏典の世界は輪廻転生の世界(⇒『日本霊異記』、『今昔物語集』)
仏教以前の古代の葬儀・・(『古事記』『日本書紀』)天若日子の葬儀に鳥が葬列に参加・・(鳥は天若日子の転生した姿)
古代エジプトの陵の参道や中国・朝鮮の陵の参道の左右に並ぶ石獣・石人の列も同じように解釈できる(※)
両面像の石像は四つ目の犬同様この世とあの世の境界に立つ
大祓えの祝詞・・天つ罪・国つ罪・・宇宙的な運航が最も衰弱したと考えられ時に行われた反秩序すなわち混沌の行為
国つ罪とされる最近親相姦や獣姦は、死者(男性)の魂が母体に入ったり各種の動物や鳥の中に入って転生し、死者が再生することを演じたもの・・
仲哀天皇の霊魂は殯宮(あらきのみや)の儀礼において、神功皇后の胎内にいる御子に移った。武内宿禰(※)がこの場で仲介者として神と人の間を取り持った。(『古事記』)
墓室内のあの世への入口に牡牛がいるのは西南アジア文化では広く見られる
古代ペルシア帝国のペルセポリス宮殿入口の(有翼)人面牡牛像
イランのミトラ信仰に由来するローマのミトラス教の儀式では、洞窟の入り口で牡牛を屠り、信者はその血を浴びた(牛は祖先獣で、万物の祖)
紀元前三千年初頭のシュメール文明では、獅子頭の聖鳥アンズ―の彫刻が神殿の入口に見られる。
巨大なアンズ―を中心に、獅子、牡鹿、野生山羊の三組の動物が左右対称に並ぶ。アンズーは大気の神エンリルを象徴したのであろう(小林登志子)アンズ―はトーテムポール最上部のサンダーバードーとや野獣の女王ポツニア・テーローン(※)を想像させる。獅子がリラは牛の頭部かもしれない。
『西遊記』の猪八戒の生い立ちにも転生のモチーフがある
厳格な一神教であるイスラム教では、神に呪われたものは豚や猿にされるので、一脈相通じるものがある
(以下 2013年の⇒干支 巳 に続く)
諸橋轍次『十二支物語』(蛇)
以下NETおさらい
十二次
Wikipedia 十二次より、以下引用古代中国天文学における天球分割法の一つで、天球を天の赤道帯にそって西から東に十二等分したもの
戦国期以降に行われ、太陽・月・惑星の位置や運行を説明するための座標系として使用された。
特に重要な用途が二つあり、
第一は木星の十二次における位置で年を記すことであり、
第二には、季節ごとの太陽の位置を十二次で示し、二十四節気の移動を説明することである。
十二辰
古代中国天文学において十二次以外の天球分割法に十二辰や二十八宿がある。
十二辰(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)は配当の方向および順序が東から西へと逆になっているが、区分領域は十二次と全く同じである。
黄道十二宮との対応
十二宮との対応
星紀 - 人馬宮(いて座)15度から磨羯宮14度まで
玄枵 - 磨羯宮(やぎ座)15度から宝瓶宮14度まで
娵訾 - 宝瓶宮(みずがめ座)15度から双魚宮14度まで
降婁 - 双魚宮(うお座)15度から白羊宮14度まで
大梁 - 白羊宮(おひつじ座)15度から金牛宮14度まで
実沈 - 金牛宮(おうし座)15度から双子宮14度まで
鶉首 - 双子宮(ふたご座)15度から巨蟹宮14度まで
鶉火 - 巨蟹宮(かに座)15度から獅子宮14度まで
鶉尾 - 獅子宮(しし座)15度から処女宮14度まで
寿星 - 処女宮/室女宮(おとめ座)15度から天秤宮14度まで
大火 - 天障宮(てんびん座)15度から天蝎宮14度まで
析木 - 天蝎宮(さそり座)15度から人馬宮14度まで
十二支
元々十二支は順序を表す記号であって動物とは関係がない。なぜ動物と組み合わせられたかについては、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説(後漢の王充『論衡』)やバビロニア天文学の十二宮の伝播といった説がある
Wikipedia「十干」より引用十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素の順列
十二支と合わせて干支(「かんし」または「えと」)といい、暦の表示などに用いられる
| 十干 | 音読み | 訓読み | 意味 | 本義 |
| 甲 | こう | きのえ | 木の兄 | 草木の芽生え、鱗芽のかいわれの象意 |
| 乙 | おつ | きのと | 木の弟 | 陽気のまだ伸びない、かがまっているところ |
| 丙 | へい | ひのえ | 火の兄 | 陽気の発揚 |
| 丁 | てい | ひのと | 火の弟 | 陽気の充溢 |
| 戊 | ぼ | つちのえ | 土の兄 | “茂”に通じ、陽気による分化繁栄 |
| 己 | き | つちのと | 土の弟 | 紀に通じ、分散を防ぐ統制作用 |
| 庚 | こう | かのえ | 金の兄 | 結実、形成、陰化の段階 |
| 辛 | しん | かのと | 金の弟 | 陰による統制の強化 |
| 壬 | じん | みずのえ | 水の兄 | “妊”に通じ、陽気を下に姙む意 |
| 癸 | き | みずのと | 水の弟 | “揆”に同じく生命のない残物を清算して地ならしを行い、新たな生長を行う待機の状態 |
『中国的実在観の研究』(木村英一著)
『中国上代陰陽五行思想の研究』(小林信明著)
『宋代易学の研究』(今井宇三郎著)
『十二支考 (上・下)』南方熊楠著 宮田登・解説/岩波文庫、1994年/ ワイド版、2003年