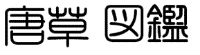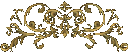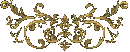巳(干支)
![]() このページは、唐草とともにある聖獣という観点で、2013年の開始時のテーマのまとめで、
ここでは十二支の巳(聖獣 蛇)を見始め、井本英一著他を読み進めたが、範囲が広く、勉強不足。細緻な学入門篇、という感じですwww。
このページは、唐草とともにある聖獣という観点で、2013年の開始時のテーマのまとめで、
ここでは十二支の巳(聖獣 蛇)を見始め、井本英一著他を読み進めたが、範囲が広く、勉強不足。細緻な学入門篇、という感じですwww。
十二支は中国の獣帯であるという。
 midosi.html十二支(中国の獣帯)ページへ
midosi.html十二支(中国の獣帯)ページへ
以下では、平凡社世界大百科事典(1988版)で「干支」などをの項をみます。
中国では,西方の文明が1月を四分
して7日(週)をサイクルとしたのに対して 三分して10日(旬)とする日の数え方が古
く殷代には行われていた。
甲骨文にト旬
とあって,ある日から向こう10日間の吉
凶を占った。十干はその10日の順序符号
である。十二支も12月の呼び名として殷
あわせて六十千支とし,それによって日
を記すこともすでに殷代には行われていた。
干は
幹,支は枝の意だという。十千と十二支
個々の文字の意味はよくわからぬか
どちらも植物が季節の推移にしたがって
変化してゆくさまをあらわすとする説が
ある。
三浦国雄+薮内清(3-p362)
十干十二支の始原
十干十二支について、十と十二
中国の十干十二支について、白川静は、日の次第は、十干と十二支を組み合わせた六十の干支で表示する
十干はおそらく
太陽を呼ぶ名とされていたらしいが、十二支が何を示すものであったのかは知られない、という。(『中国古代の文化』講談社
1975 p273)
十干つまり甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸は十日の呼称であるという。十二支のことは不明とされるが、現実に本来の漢字とは何の関係もない動物が当てられ、殷時代から十干とともに、変わることなく用いられてきた。
白川静によると、十二個の漢字は動物とは何の関係もない。古代イランのような西南アジアの動物の呼称であるかもしれないという。
古代イランは年代的に新しいので比較の対象にはならないが、メソポタミアやアナトリアやエジプトの古代語とも縁がなさそうである。
古代中国でも古代西アジアと同じように、十と十二の数が併存し、十新法のほか十二進法も用いられ、二つの最小公倍数は六十で、六十年での本卦がえりは、中国より古いエジプトにもあった。
ギリシアのエフェソスのアルテミス女神の神殿は12年ごとに焼いて建て直した。
王の統治期間は宇宙の運航の周期と一致すると信じられたので、十ニは特別の意味を持っていた。
(J・G・フレイザー『金枝篇 死にゆく神』1911 p47-49)
東洋で太歳(たいさい)とか夜中の明星と呼ばれ、古代世界で王の星と言われた木星の公転周期は11・86年
太歳はまた神の子として生まれ変わった王をも指した。
ヘロドトスによると、一年と言う単位を発見したのはエジプト人であり、一年を十二の部分に分けたのも、エジプト人が最初である。 十二神の呼称を定めたのも、エジプト人が最初であるという。
トーテム獣と十二神
エジプトは最初は十二の国(ノモス)に分かれていた。それぞれの国はトーテム獣を持っていた。王の即位式や重要な祭りには、人々はトーテム獣と共に参加した。(日本では植物トーテムの文様をつけた紋付きをきる)
頭にトキ・犬・ヒヒ・ハヤブサ・羊などの面を被り、四肢と胴は人間の像がそれで、聖俗の境界に出現する合成像(ハイブリッド)が本来の姿であった。
竿の先端に置いたトーテム獣の模型はやがて、竿先から垂らす獣皮にとって代わられた。⇒旗・幟へ発展
イラン神話の暴君ザッハークは、千年統治したが、両肩にはやした蛇が、毎日二人の若者の脳を食糧とした。
鍛冶屋のカーヴェが鍛冶仕事の時に膝に掛ける牛の皮を槍の先につるした。カーヴェの旗はイラン神話の歳最初の王朝の旗。牛はイラン王家のトーテム獣。(黒柳恒夫『ペルシアの神話』1980)
(フィルドゥスィー『王書』岡田恵美子訳岩波文庫1999 p52-56)
ヘロドトスは言う。ヘラクレスの名はギリシア人がエジプト人から受け入れた。エジプト人が自ら言うところによれば、ヘラクレスが属するとされる十二神が八神から生まれたとき以来、アマシス王(前570~526)の時代まで、実に一万七千年が経過している。(二・43)
ヘロドトスには「十」にもとづいた十神については何の言及もない。
エジプト人が知っていた黄道帯の十二宮には、春分から始まって、猫・ジャッカル・蛇・スカラベ・ロバ・ライオン・羊・牡牛・ハヤブサ・ヒヒ・トキ・ワニの鳥獣と聖虫が配されていた。
バビロニアの十二宮には、祭司・牡牛・羊飼い(双子)・カニ・竜(ライオン)・イシュタル女神(麦の穂)・天秤・蠍・射手(半人半馬)・羊・船頭(水がめ)・アルゴー船(魚)が配されている。
十二という数
中国の十二支はすべてが鳥獣蛇のような動物であるが、それに近いのはエジプト。
バビロニアと欧州のものは、動物が限られている。
ギリシアのオリュンポス山に帰って行った人々の魂は、女神の周りに侍る野獣になったが、
ゼウスを中心とするオリュンポス十二神
として代表されるようになった。
男神六柱(ゼウス・アポロン・アレス・へパイトス・ヘルメス・ポセイドン)
女神六柱(へラ、アテナ、アプロディテ、アルテミス、ヘスティア、デメテル)
十ニという数が先行したらしく、細部に移動がある
ヘスティアは炉の神であるが、神話になく、デメテルは大地母神で、より古い時期の野獣たちの女主人であったかもしれない。
ハデスはゼウスとポセイドンの兄弟であるが、冥府の神として地下にとどまった(M・ムニエ『ギリシア神話』原章二・松田孝江訳八坂書房1979)
ルキウスはエジプト再生の女神イシスの前で、十二獣を転生して人間になった
(アプレイウス『黄金の驢馬』呉茂一・国原吉之助訳 岩波文庫1957 下p164)
仏教では薬師信仰において十二神将が信者を擁護する。病人が治癒・再生するためにたどる一つ一つの段階を神格化したもの。
各段階の存在は、原初は何らかの鳥獣で、祖先動物であったと考えられる。
仏教の十二天は、初期のものは十二支獣とは関係のない獣に乗っている。仏教の十二神将も十二天も、中国仏教の所産ではなく、インド仏教、ヒンドゥー教からの伝統である。
エジプト人は十太陽年と六十太陰年と閏として入れるニ三太陰月を足したものが、同じ周期であると考えていた。
王(ファラオ)はこのような宇宙の運航と連動していたので、即位後三十年にジェド柱をたてるセド祭りという儀式を行った。
中国では、十干十二支は五行思想や陰陽道と結びついて壮大な体系を作ったが、他の文化圏には同じ現象は生じなかった
山の神と野生動物
山の神という概念は、たいていは女神で表象される。
日本では盂蘭盆に帰ってくる祖先は、鳥獣の姿を取らないが、発生的にはそうではなかったことは見てきた通り。
白川静『字統』によると、陵とは神霊の降下を迎えて祭るところで、その地は山が平坦に近付く所。阝は神の梯子の形である。
死者の魂は、死去した場所で一定の日を過ごし、山に帰る。
死霊は、女性原理である山の神の胎内に入り、月満ちて鳥獣として生まれ出る。猟師は狩猟の後必ず山の神に猟獣の内臓その他を供え、山の神の許しを請う。おこぜ(虎魚)を供える。おこぜは老いれば蛟(竜)になる(最強の生物、虎、竜)
古代クレタ文明やキュプロス・ミュケナイ文明には、ポツニア・テ―ローンと呼ばれた山の神がいた。(『古代の神々』E・O・ジェームズ1960)
英雄ヘラクレスの功業(『ギリシア神話』アポロドーロスは十二でなく十という)は、本来は十の動物が関係したので、イランのウルスラグナやインドのヴィシュヌの十変化と同じものであった。
不死の獅子の皮、九頭の水蛇を殺す、黄金の角を持つ鹿を生け捕りにする、猪を生け捕りにする、鳥を退治、(牛小屋の掃除)、白い牡牛を生け捕りにする、人食いの雌馬を生け捕りにする、(アマゾンの女王の帯)、三頭三身の
ゲリュオネスの赤い牛を生け捕りにする、(金のリンゴ)、冥界の番犬ケルベロスを地上に連れて帰る
ケルベロス(一つの胴に頭が二つ付いた犬)=サンスクリット語でシャルバラス「雑色の」=死者を冥界に導く四つ目の犬の形容辞
堯(ぎょう)=中国神話のヘラクレスは十日(じゅうじつ 10個の太陽)がでて旱魃が生じたので、羿(げい)に命じて十日を射させた。
人民に害をなす竜に似た動物、人の形をした怪獣、水火の怪、大風(大鳥)、大豚、九つの頭を持つ大蛇を殺したので、人間は喜んで天子にした。
(『山海経』金関丈夫『太陽を征服する伝説』
十個の太陽は一人の女神羲和に支配される。
羲和は山の神で十日も本来は十の鳥獣
(小川琢治)
おまけの百獣楽園

江戸の 龍虎図(日本、中国)を見たおまけです
![]() ただ今は、2025年の10月17日で、このページ作成から12年後の、巳年になっています。
ただ今は、2025年の10月17日で、このページ作成から12年後の、巳年になっています。
- 井本英一著『死と再生―ユーラシアの信仰と習俗 』を読むmidosi_imoto.html
- 諸橋轍次『十二支物語』(蛇)を読む midosi_morohasi.html
エジプト、ギリシア、マヤ のゾディアック zodiac.html
(獣帯)
(黄道十二宮)
立川武蔵さんを読む../lion_tatikawa.html(以下 7p) インド
荒俣宏さんを読む../lion_aramata.html (以下 6P) インド、東南アジア
エジプトの蛇女神../wadjet.html(以下2p)