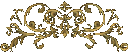西欧中世の美術
「15のテーマで学ぶ 中世ヨーロッパ史」
堀越宏一・甚野尚志 共編著
ミネルヴァ書房 2013年01月
著者紹介
堀越宏一 主著『中世ヨーロッパの農村世界』山川出版社 世界史リブレット、1997
『中世ヨーロッパ生活誌』日本放送出版協会 NHKカルチャーアワー 歴史再発見 2008
『ヨーロッパの中世 5 ものと技術の弁証法』岩波書店 2009
甚野尚志 主著『隠喩のなかの中世-西洋中世における政治表徴の研究-』弘文堂 1992
『中世ヨーロッパの社会観』講談社学術文庫 2007
『中世の異端者たち 世界史リブレット』山川出版社 1996
『十二世紀ルネサンスの精神-ソールズベリのジョンの思想構造-』知泉書館 2009.
 以下目次読書(20181228)
以下目次読書(20181228)
本書の意図
通史でなく、一千人に及ぶ中世の歴史の中で作り上げられた中世ヨーロッパ文明を構成する諸要素を描き出すこと
中世ヨーロッパ世界では、宗教と美術、音楽などの芸術が社会と密接な関係があった事からもわかるように、その文明の内容を理解するためには狭義の歴史学のテーマだけでは不十分→隣接する分野のテーマも加える
領域横断的に論じる、概説書
なぜ中世ヨーロッパ文明なのか
普遍性を持つ特別な文明をして考察することが多い「ヨーロッパ中心史観」批判→しかしながらグローバル化の中では、様々な面での欧米的なスダンダートの優越性もまた否定すべくもない
ヨーロッパの文明の思想と文物の起源はどこにあるのか。古代オリエント社会は、証書等すぎる過去であろう。古代ギリシアとローマの文明は、その後のヨーロッパ社会がさまざまな方向に展開する基礎となる要素を数多くもたらした。
プラトンやアリストテレスの哲学は今もヨーロッパの詩雄の基盤であり続けている。
それらを含み込みつつ、 その後のヨーロッパ文明を形成する大多数の要素は、5世紀末から115世紀に及ぶ中世一千年、とりわけ紀元千年前後から14世紀半ばまでに時期に生み出され、ヨーロッパ各地に定着していった、(p3)
ローマ・カトリックによるキリスト教化
古代から中世への移行を考える王道的な問題設定
聖戦理念の出現とほぼ同時期に、異端への過酷な弾圧が始まった。両者は表裏一体のもの。教義を明確にするために学問が発達し、そこから教育機関としての大学が生まれた事も重要。典礼の側面でも楽器を伴う在り方が、その後の西洋音楽を発展させる契機となった。
ローマ・カトリックの規範的な意義を示す。
多様な中世ヨーロッパ文明
1970年ごろを境として、政治も経済も、それだけでは歴史を規定する要因ではありえないという認識が共有されるようになっている。パラダイムの転換。
文明を規定する要素を区分して再考するアイディア・・
ロバート・バートレット著『ヨーロッパの形成― 950年-1350年における征服、植民、文化変容』(伊藤誓・磯山甚一訳、法政大学出版局2003)
潔いほど個々の要素を並立させている 複眼的に捉える。
・・北フランスなどの西ヨーロッパの中核地域起源に起こった様々な文明的な要素が、10世紀後半から14世紀にかけて、その外側に位置するヨーロッパ諸地域に伝播し、現在に至るヨーロッパ文明の個性が誕生したころを明らかにしている。
中心と周辺
超地域的な国際性と法的な形式を備えて、等質性と複製可能性を持つ原型が、フランスを中心とした西ヨーロッパに発生し、ヨーロッパ世界全域へ拡大していった。中央が辺境を群意j力によって征服したわけではない。
しかい、 イベリア半島のイスラーム教徒に対する軍事征服は、近世以降の植民地化の問題が早くも現れている。(p7)
中世ヨーロッパ文明の射程
ドイツのケラリウスが『普遍史』(1683年)で、歴史の過程を古代、中世、近代の三つに分けたて以来の伝統的時代区分。
ジャック・ルゴフ『中世とは何か』(池田健に、菅沼潤一訳、藤原書店、2005)・・「長い中世」
・・中世史の泰斗が対話形式で自身の研究を回顧しながら、現代まで続く西欧文明の中核をなす都市、大学、商業、芸術などの原点が中世にあることを強調する。
参考文献
『中世ヨーロッパを生きる』(東京大学出版会、2004)・・姉妹編
『西洋中世資料集』ヨーロッパ中世史研究会編(東京大学出版会、2000)
R・W・サザーン著『中世の形成』森岡敬一郎・池上忠弘訳(みすず書房、1978 原著1953)
・・10世紀後半から13世紀初めの時期に、西ヨーロッパ社会が確立したことを語っている。とりわけ、教会と学問・思想がそこで果たした役割を重視している。
C・ド―ソン著『ヨーロッパの形成―ヨーロッパ統一史叙説』野口啓裕・草深武・熊倉庸介訳(創文社、1988 原著1932) ・・西欧文化の決定的転換点を11世紀に置いて、ローマ・カトリックとゲルマン的要素を基盤としてヨーロッパ文明が形成されてたことを論じている古典的著作。ビザンツとイスラムから受けた影響を重視していることが特徴的。
J・ル・ゴフ著『中世西欧文明』 桐村泰次訳 (論創社、2007 原著1964)
・・西欧世界で形成された中世文明とは何か、という問いに対し、通史的な叙述ではなく、様々なテーマから歴史人類学的に論じた概説。
| 第1章 | キリスト教化と西欧世界の形成 | 多田 哲 |
| 第2章 | ローマ・カトリック教会の発展 |
甚野 尚志 |
| 第3章 | 中世後期の宗教生活 |
印出 忠夫 |
| 第4章 | 戦争の技術と社会 |
堀越 宏一 |
| 第5章 | 貴族身分と封建制 |
桑野 聡 |
| 第6章 | 文書と法による統治 |
岡崎 敦 |
| 第7章 | 西欧的農業の誕生 |
丹下 栄 |
| 第8章 | 都市という環境 |
徳橋 曜 |
| 第9章 | ラテン・ヨーロッパの辺境と征服・入植運動 | 足立 孝 |
| 第10章 | 衣服とファッション | 徳井 淑子 |
| 第11章 | 融合する食文化 | 山辺 規子 |
| 第12章 | 都市と農村の住居 | 堀越 宏一 |
| 第13章 | 知の復興と書物の変容 |
甚野 尚志 |
| 第14章 | 見えないものへのまなざしと美術 | 木俣 元一 |
| 第15章 | ヨーロッパ音楽の黎明 | 那須 輝彦 |
![]() このなかの、第10章を以下へ。
このなかの、第10章を以下へ。
第10章衣服とファッション
徳井 淑子
1.ヨーロッパ服飾の誕生
上下衣二部形式の定着
身体に密着した上着に、足を別々に包むズボンを組み合わせる上下衣形式、窄衣形式:
寒冷のヨーロッパ大陸にすむゲルマン民族の服飾にさかのぼる
中世がその後のヨーロッパ服飾を決めた時代であることは、衣服を表す言葉によっても明らか
シュミーズ、コート、ジャケットなど12~14世紀に現われる
古代ギリシアやローマの衣服は懸け衣形式、身体との緩みによって生じる襞の美しさを追求した衣服
身体造形へのこだわり
腕に密着した筒袖とするために、袖を縫う。着装のたびに肘から手首まで縫い合わせ、脱ぐ時にそれを解いた。糸と針を持ち歩いた。
衣服の製作と産業
2.社会表象としての衣服
素材による階層・集団の明示
人々の間の差異を示すのは、衣服の形態と言うよりも素材と色
スカーレット、ケルメス(ケルメスカシに寄生するカイガラムシ)染料で染めたフランドル産の赤い毛織物→14世紀のシャンスリエ(大法官)のユニフォーム、15世紀の枢機卿の衣の色
色の違いは素材の違いでもあり、ゆえに色名は織物の呼称になることが多い
素材の序列として、さらに中世で独特なのは衣服の裏に貼られる毛皮の場合。ヴェール、グリ、アーミン・・


色によるしるし付け
衣服の色は、連帯を育むと同時に社会から排除する
ユダヤ人にルエンと呼ばれる黄色い布、娼婦に縞柄の腕章→黄色と縞柄への嫌悪感→道化師や奉公人、芸人、子どものみの服装(子どもは道化師に類似した存在)
衣服の見頃を左右で色分けするミ・パルティも道化と子ども、奉公人
緑色ケルト人の樹木崇拝に由来し五月祭に着用する衣の色 人生のサイクルとしては青春の色 未熟、狂気
運命女神に多色の縞のドレス(気まぐれ、不合理な行動を示す)
複数の鮮やかな色を配置することへの嫌悪感は、黒の流行の一因に、また今日のヨーロッパ人のクロモフォビア(色に対する禁欲的な態度)を生み出した理由の一つ


文化表象としての衣服
儀式・儀礼における服飾のシンボル
中世の『薔薇物語』人の感情や徳目を擬人化して描く文学の手法、
教会建築の装飾に、七つの大罪や徳目を人のかたちに表して表現する手法→抽象的なものを具体的なかたちをもって表そうとする中世人の心的傾向
目に見える衣服を何らかの表象としてみる傾向も、このような心性としてみることができる
手袋 (権利や権限を象徴)の授与
ラテン語の手という語が権力とか権威とかの意味をもった事実と関わる
女性が袖(愛の証)を贈る習慣:それを兜の先や槍の先に結び付け、あるいは盾の裏に鋲で留め戦う
ジェンダー表象
女性が決して着用することのないズボンを男性性と強く結びつける(13世紀)ズボンは女性より優位にあるべき男性のシンボル ズボン争奪戦
黒の好尚と近代服飾の萌芽
黒が洗練された色として認識されるようになるのは、14世紀末から15世紀 中世末期の流行色に
黒の流行を牽引した人物として有名なブルゴーニュ公フィリップ・ル・ボン(1396~1467)・・父の喪に服して黒いプールポワンなどを着用、この色を好む背景には時代の深い憂愁感がある(p222)
個人の心情を示すドゥヴィーズ(紋章を校正する図柄と色彩・標語)14世紀末から王侯貴族の間に流行
夫を亡くしたヴァレンティ―ネが選んだ如雨露あるいは水滴文は、15世紀に広く流布した文様
14世紀末から15世紀初頭にかけて王侯貴族に用いられたウープランドは、ドゥヴィーズの表現の場となり、そ時々の気持ちがさまざまな図柄となって表された、そこに文学趣味の介在する様子には、教養に裏付けられた高度な遊戯が感じられる(p225)

図10‐15 カンナと水準器とホップのドゥヴィーズを衣服に表したプルゴーニュ公Jean Sans Peur
出典: フランス国立図書館『驚異の書』1411年頃
・・王室とブルゴーニュ公国の確執、 王室派の結束(枝の筋)をカンナ」で削り取って④結束を崩壊させてやるという意思表示
コラム 中世の子供服
フィリップ・アリエスの『子どもの誕生』(原著1960邦訳1980)
有名な言葉:中世の子供は産着を脱ぐとすぐ大人と同じ服装をし、子どももはさしずめ「小さな大人」である
→中世に子ども世代を特徴付ける服装が皆無であったわけではない。
ゴネル:細長い長方形の布に頭を通す穴をあけ、両端を旨と背に垂らして両脇で止めつける
子ども服の特徴がはっきり表れるのは色の使い方:黄色や緑や縞の使い方の他に、赤い服や黒い帯が目立つ
赤い珊瑚(ルビ-・ヒイラギの実)赤いものは赤いものに効く、琥珀のお守り、黒いものは黒いものに勝つ: 黒檀の揺りかご
新生児の産着:ミイラの様に巻きつける・・不用意に動いて怪我けがをしないように・身体整形にこだわる意思
「なぜロバはあんな大きなお耳をしているの」「それはね、お母さんが頭巾を被せてあげなかったからよ」(p229)
![]() 「被り物の整形機能」・・なるほど、そんな機能が・・
「被り物の整形機能」・・なるほど、そんな機能が・・
以前読んだ本は「色で読む中世ヨーロッパ」 (講談社選書メチエ)(2006)*
「中世ヨーロッパにおいて、どのような自然・社会環境の中で色彩感情が生まれたのかを解説している」(p226)
『涙と眼の文化史―中世ヨーロッパの標章と恋愛思想 』– 2012 東信堂
「中世末期の服飾文様の源泉となったドゥヴィーズについて、文様の意味と伝播について述べている」
『色彩の紋章』–
悠書館 2009 シシル Sicille (原著1528), 伊藤 亜紀・ 徳井 淑子 (訳)
「15世紀末期から、16世紀初期にまとめられた色彩意味おrんで、中世末期の豊かな色彩語と色彩感情を知る事ができる」(p226参考文献)
『縞模様の歴史―悪魔の布 』M・パストゥロー Michel Pastoureau (原著1993), 松村 剛 ・松村 恵理 (訳)
(白水uブックス) 新書 – 2004
「縞模様をめぐるヨーロッパ文化史であり、中世に縞模様が嫌悪されたヨーロッパ人の心性につい触れている」
『青の歴史』M・パストゥロー Michel Pastoureau (原著2000), 松村恵理 ・松村 剛(翻訳)– 2005
「青が中世に発見された色であること、また中世末期に黒の好尚が起こったのち、16世紀に今日に至る黒服の歴史が始ま宇ことを陳べた色彩文化史である・(p226参考文献)
(「BOOK」データベースより)
「ギリシャ・ローマの人々にとって、青は不快な野蛮の色だった。現代では、青は、最も好まれる色として勝利を収めている。フランスの紋章学の鬼才・パストゥローが、古代社会から現代にいたる青の“逆転の歴史”を、聖母崇拝と青、フランス王家の紋章への青の採用、宗教改革以後の倫理規範と青、さらにはジーンズと青など、西洋史のなかの興味深いエピソードとともに鮮烈に描き出す。」
![]() 最近の本
最近の本
『赤の歴史文化図鑑』
ミシェル・パストゥロー (著), 蔵持 不三也, 城谷 民世 (訳)2018 原書房
(内容紹介)「
赤は、ヨーロッパにおいて人々が塗料としても染料としても最初に扱うことを覚えた色である。
物質、社会、芸術、夢想、象徴、どの観点から見ても、長いあいだ「きわだって」もっとも豊かな色でありつづけた。」
――
「赤」という色について、類がない充実した内容
旧石器時代から現代までを眺望し、「歴史書であり、言語表現から、日常生活や社会的実践、科学的知、技術的適用、宗教的倫理、さらに芸術的創造をへてシンボルへといたる、長期的かつ多角的な赤の研究をした」本書は、その歴史的・文化的視野において異彩を放っている。
「赤」という色だけについて、これほど充実した内容を披歴した研究書は他に類がないだろう。 ―「訳者あとがき」
『薔薇物語』
http://weblioteca.uv.es/
https://www.tengyu-syoten.co.jp/book/310017
第14章 見えないものへの
まなざしと美術
木俣 元一
1 中世美術の機能
美術の役割
中世美術のすべてが「文字の読めない人々」のために作られたわけではない
写本などは文字を読める人のためにつくられた
イメージを「読む」ためのある種の「リテラシー」が必要とされる
どのような環境や背景に置かれていたか
作品の周りにあった当時の社会的なコンテクストを重視するアプローチ
美術作品とそのコンテクスト
美術館に置かれたものは他に居はどこにも行き場のなくなった存在→「アート」
中世の個々の作品は、必ず特定の場所を与えられ、特定の機能を持っていた
見えないものと人間をつなぐイメージ
中世の美術作品が果たしていた機能は巾広い
「見えないもの」と人間の間を結ぶことを目的とした美術作品の需要が大きかった
2 彫像と人々のまなざし
図14‐1 シャルトル大聖堂、西正面「王の扉口」(12世紀中ごろ)chartres.html
ステンドグラスは容易に受け止められるが
ゴシック大聖堂の建築を覆う大量の彫像への違和感
図14‐2 ランス大聖堂、西正面(13世紀中頃)
近くで見せる彫像のリアリティ
ランス大聖堂西正面柱頭扉口の左右

図14‐3 ランス大聖堂、西正面、中央扉口(13世紀中頃)

図14‐4 ≪受胎告知≫ランス大聖堂、西正面、中央扉口、右側の壁面の彫像(13世紀中頃)
遠くから見るための彫像
図14‐5 ランス大聖堂、西正面、バラ窓の周辺
図14‐6 クロ―ヴィスの洗礼、ランス大聖堂、西正面、王のギャラリー(近代のレプリカ)
3 黙示録の挿絵とヨハネの幻
ヨハネの幻
聖書の中で最後にある『ヨハネの黙示録』 ヨハネというキリストの弟子だった人物が、エーゲ海のパトマス島に流されたときに、そこで見たこの世の終わりの関する幻
(『ベアトゥス黙示録註解』写本、ブルゴ・デ・オスマ、大聖堂美術館(1086年完成)
El Burgo de Osma
天空を飛翔するヨハネの霊魂
黙示録の冒頭でヨハネが天上にいる神を霊的な視覚によってみるところ
挿絵は研究する修道士たちに黙示録の内容を解説する役割を果たしている
天使に「だっこ」されるヨハネ
新しい読者たちはヨハネになりかわって幻を目撃しているかのような臨場感を得ようとした
4 聖遺物とみえないもの
図14‐9 腕型の聖遺物容器(13世紀中頃)聖遺物とは何か
信仰の核を形成していた
内容物がなんであるかを示すためのものでない
聖人が祝福を与える腕と手を模したもの
ルイ9世が1239年に入手したキリストの茨の冠などを収容するために建造された(1248年献堂)
美術の必要性
聖遺物を出発点として、聖遺物に関わる見えないものを提示

図14‐11 マギの聖遺物容器(正面)ケルン大聖堂所蔵(1200年前後)

図14‐12 マギの頭蓋と王冠、≪マギの礼拝≫、≪キリストの洗礼≫ケルン大聖堂所蔵
Shrine of the Three Kings
ケルン大聖堂とマギの聖遺物容器

マギの頭蓋と王冠の≪マギの礼拝≫での第4の人物「オットー王」が持つ小さな箱の蓋にはめ込まれていたもの 図14‐13 プトレマイオスのカメオ ウィーン、美術史美術館所蔵
美術とモノの協力関係
宝石やカメオに人間の手で彫り込まれたイメージがあったとしても、それが天体の位置関係によって生じたり、あるいは所有する人間の想念を映し出したものであるという発想が存在していた。
奇蹟によって生じた自然物
5 中世美術の新たな理解に向けて
中世においては、「美術という見えるものを媒介としてさまざまな見えないものとどのような関係を作っていたのか」
コラム14『エクレシアとシナゴーガの彫像

シナゴーガ(ユダヤl教会)
ランス大聖堂、南正面(13世紀中頃)
キリスト教の信仰の下での国家や都市における理想的な統治理念
ユダヤ教徒たちは「シナゴーガ」の像が示すように従順にキリスト教的君主の統治下に置かれる

ストラスブール大聖堂にあったシナゴーガ像とエククレーシア像。ノートルダム美術館蔵。
Ecclesia and Synagoga
ヨハネの黙示録 (講談社学術文庫) 文庫 – 2018/5/10
小河 陽 (翻訳)
『ベアトゥス黙示録註解―ファクンドゥス写本』 大型本 –岩波書店 1998
大高 保二郎
, 安発 和彰 (翻訳), J.ゴンザレス・エチェガライ
『ゴシックの視覚宇宙』 名古屋大学出版会 – 2013
木俣 元一
内容説明
西洋中世において爆発的に拡大したイメージの世界は、何を顕わにし、それを観る者にいかなる経験や認識をもたらしたのか。黙示録写本、ステンドグラス、聖遺物など、イメージが切り拓いた多様な視覚宇宙を探究し、「見えるようになること」を根底から問い直したゴシック美術論。
目次
第1部 隠蔽から開示へのレトリック(レヴェラティオをめぐるレヴェラティオ—視覚的タイポロジーの試み;「天に開かれた門」—黙示録写本の挿絵と読者/観者の内的ヴィジョン ほか)
第2部 記憶と想起のトポグラフィー(イェルサレム・コンスタンティノポリス・パリ—サント=シャペルとその装飾;過去の物質的引用—サン=ドニ大修道院長シュジェールのスポリアを中心に ほか)
第3部 「鏡」としてのユダヤ(反転した自己表象—「ユダヤの帽子」の解釈をめぐって;「恐るべき不信仰」とイメージの聖性—聖ニコラウス像を罰するユダヤ教徒)
第4部 聖顔:不在と現前のディアレクティック(痕跡としてのイメージ—奇跡的イコンと刻引のメタファー;「顔と顔とを合わせて」—一三世紀イギリス写本における聖顔と祈念 ほか)
「BOOKデータベース」 より
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalipsis数字と色 本の至るところに存在する多数のシンボルの中で、2つの特徴が際立っています:「数字」と「色」。