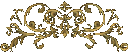![]() 饗庭孝男さんの、『ヨーロッパ古寺巡礼』の目次読書に次いで、饗庭さんがヨーロッパについて最初に書いた本『石と光の思想』の目次読書・・
饗庭孝男さんの、『ヨーロッパ古寺巡礼』の目次読書に次いで、饗庭さんがヨーロッパについて最初に書いた本『石と光の思想』の目次読書・・
『石と光の思想』の目次読書
『石と光の思想 ヨーロッパで考えたこと』
饗庭孝男著(1971年4月勁草書房→平凡社ライブラリー1998年11月)
※後者で読む
表紙の一文
「リルケ、プルースト・・・・あるいはロマネスクの教会、ジオットの壁画 。
人を拒否する「医師」と人が求めたy間内「光」の好天にあらわれる芸術の数々。その無数のきらめきを通して、ヨーロッパ精神の根底を見つめる。」
目次読書
Ⅰ
石の思想
Ⅱ
パリの孤独
シャルトル
ロマネスク教会巡礼
ブルターニュ
Ⅲ
フェルメールの世界
ネーデルラントの狂気
Ⅳ
フィレンツェの春
ヴェネチアの光と影
パドヴァ
ミラノの詩人
アシシの丘
ラヴェンナの月
Ⅴ
スペイン、わが愛
Ⅵ
モーツァルト論
アディロン・ルドン論
あとがき
Ⅰ 石の思想
ヨーロッパで私が初めて感じたことは、人間が石造りの建物に住んでいるという事実から受ける奇妙な嘔吐感、または眩暈感であった。(書き出しの一文p10)
石は自然の脅威に対しては堅固に有機的存(人間)を守るが、同時に石造りの建物の内部では明確に人間を拒否しているということ
石の非情な本質
「石」に囲まれて人間が生きているという事実
石が人間を守るという働きよりも、それを拒否するという働きに注目せざるを得なくなった(p11) 人間:有機的存在 生の機能を犯してゆくその非常性は、人間を、ただあること自体において即物的に否定しようとする沈黙の暴力を持っている(p11)
 このヨーロッパに対する感想であるが、現代のコンクリートのマンション(公園に隣接している)に住んでいる身としては、ヨーロッパに行ったからといって、余り感じとれないのである。
このヨーロッパに対する感想であるが、現代のコンクリートのマンション(公園に隣接している)に住んでいる身としては、ヨーロッパに行ったからといって、余り感じとれないのである。
木となれ合い、自然と調和している日本人にとっては「死」は多くの一つの自然の帰結に映じるのに反して、ヨーロッパにおける死の意識は、一つの暴力とも力動的な作用ともなって人々の心に生きている。そこではじめて「石」を媒介にして「生」と「死」と対話を始めるのだと私は思う。(p16)
ヨーロッパの人間は、ニ十歳を過ぎるまで、実に美しい容貌をしたものが多い。幼年・青春・中年・老年の、美から醜への移行は、実に画然とした段階を持っているように思われた。しかもその意汚行のプロセスは彼らが美を”喪失してゆく”という表現よりも、「時間」の数学的浸食に、美を”深く蝕まれれ”、”食い荒らされてゆく”という表現の方が一層適切に思われる。(p35-38)
ヨーロッパにおける時間は、きわめて”能動的”であり、それは”時は過ぎてゆく”という抒情的表現よりも、人間を貪欲に食い尽くし無に帰するまで我々を追ってくるのである。「時間」は、ここでは、唯一無二に生きている存在である。それはむしろ生きている「死」である。(p39)
日本では「生死重大、無常迅速」では、気を一にしても、日本では、むしろ逃れがたい時間の脅迫から、一挙に空間的なものによって移行しようという姿勢が強い。(p40)
 このあたり、日本における時間の観念とは何かということは、稿をあらたに、ということで終わって、ヨーロッパ的な「時間性」がどこに関わっているかを考える、と続く
このあたり、日本における時間の観念とは何かということは、稿をあらたに、ということで終わって、ヨーロッパ的な「時間性」がどこに関わっているかを考える、と続く
スペインのマラガ: 地中海の眩むような光、青さ
幸福とでもいうべき感情が光と青さに釣り合うようにあらわれた。(p42)
光に対するヨーロッパ人の憧憬は、憧憬と呼ぶより信仰に近く、一種のオルフィスムの様に彼らの中に生きている神話的事実である。(p42)
向日性
アテーナイの国立博物館の、ギリシャ期の比類なく美しい彫像
埋葬の悲しみを刻んだ映像(レリーフ)にある人々の悲しみは張り詰めた感情の、それでいて静謐な表現は感動を誘わすにはいられない。
哀しみの美の永劫の循環(p50)
人間に発し人間に帰ってゆくほかのない人間の運命の、
「耐え忍ぶ」思想が美しい芸術的定着を成し遂げた(p51)
ピエタを描くキリスト教芸術の思想
マリアの無惨悲痛な苦悩が、レアリスムによって見事に描かれる。
この苦悩の癒される世界が目に見えぬ形であらわれている。もう一つの世界をもって初めて完全となる世界の空間。
復活の予知、栄光の告知が、苦悩の延長線上にあらわれ、時にその画面を光で包んでいる。(p52)
キリスト教は、太陽から裸(あら)わに落ちてくる「光」ではなく、別種の「光」を考え出した。(p54)
自然の「光」とキリスト教の「光」も、また長いヨーロッパ精神史の中で、さらに各個人の内部で、絶えることのない対話を続けている。(p55)
 以上、冒頭の章47ページからの文学的な表現であった・・
以上、冒頭の章47ページからの文学的な表現であった・・
以下こちらのテーマによる「ロマネスク教会巡礼」の項の抜き書き読書に入るが、その前に、あとがきから少々
私はヨーロッパを論じたのではいささかもなく、一個の私という存在と、共鳴音(レゾナンス)を発したヨーロッパを語った(p356)
<内なるヨーロッパ>
私はかの地にいても、自分はどこでも生きることができると思い、自分の生き方を決定的に変えるものは何もない、と感じていた。
にもかかわらず書きたいという内部からの強い促しは、異なった世界における自己確認という形をとりながら、それまで自分の内部で生き続けてきたささやかな思想との出会いの中で対象化できるだろうかという自問であった。
私が戦後に受けた価値体系の崩れを、ヨーロッパ精神史の堅固な≪秩序≫の核を作り上げた中世と対比させることによって、明らかにしたかった(p357)
ヨーロッパについて書いた最初の本である
「ヨーロッパ古寺巡礼」( 新潮社):地方と中世の文化を中心に書いた
「幻想の都市―ヨーロッパ文化の象徴的空間」(新潮社→講談社学術文庫):13世紀に始まる都市という近代の文化を示す有機的な構造体を論じた
これら二著への先駆であり、仕事の出発点であった
芸術に関する個別の仕事、諸領域の中心にこの本の「パリの孤独」がある
ロマネスク教会巡礼
―その黙示録的世界
(p111‐143) 以下「ロマネスク教会巡礼」の項の教会名の抜き書きであるが、オーヴェルニュとヴェズレーの話が興味深かった。オーベルニュはリヨンから
以下「ロマネスク教会巡礼」の項の教会名の抜き書きであるが、オーヴェルニュとヴェズレーの話が興味深かった。オーベルニュはリヨンから
ヴァルカブレェールの
「サン・ジュスト教会」(p111)
「サン・ベルトラン・ド・コマンジュ教会」から1キロ (p113)
パリの
サン・ピエー・ド・マンマルトル教会
サン・ジェルマン・デ・プレ教会(p114)
パリ北方のロワイヨモン
オーヴェルニュの
「オルシヴァル教会」(p114)
クレルモン・フェランの「ノートルダム・デュ・ポール教会」→2015k/Notre-Dame_du_Port.html
サン・ネクテールの教会(モン・コルドナールの山上)※見事な柱頭彫刻
イソワールの「サン・ポール教会」※「迷える羊を救うクリスト」という柱頭彫刻・・ゴール的な諧謔と哄笑を想起させる(p123)
プロヴァンスの修道院(クロワトール)
アルルの「サン・トロフィーム教会」(p126)
「モンマジュール修道院」(p128)
(知らない:ノルマンディーノ「ブランシュ修道院」、 ラングドックの「モワサック修道院」、
ルッシオンの「サン・ミシェル・ド・クシャ」、スペインの「セント・ドミンゴ。デ・スィロス修道院」)
修道士(モワンヌ)はもともと独りという意味からきているし、修道院(クロワト―ル)という一つの名も閉じるという意味からきている。したがって、深く自然の中で「独り閉じこもる」という意味が修道の意味であると考えてよい。(P127)
ヴェズレーの「聖マドレーヌ教会」(p134)ロランが、麓に、かって中世に多くの巡礼者を集めたこの丘に生涯の終わりを生きたことを意味深く受け取る。
「孤独と遺棄の感じ。良心の糾明をし、一生の仕事と作品を振り返っている。縋りつくことの出来るものは何もない。・・・クリストフもベートーヴェンもどこに行ってしまったのだろう。」(ロマン・ロランのメモ)
神の前にただ一人立っているロランが好きである(p134)
私には丘の上にある教会はいずれも心にある喜びを与える。(p136)
故郷クラムシ―の「サン・マルタン教会」(ロランの墓)
「クリニュー修道院」の三層に及ばない二層ではあるものの高さの印象を与えることは変わりがない
遥かな歴史のかなた、ヴェズレーは、スペインのサンチアゴ・デ・コンポステラで発見された聖ヤコブの墓を目指した最初の十字軍の騎士たちの出発の地であった。
城と灰色の交互にはめ込まれたくさび石の模様が、コルドバの「メスキータ大聖堂」のイスラム風の模様を想起させ、非現実的な幻想感をいだかせ、優雅で明るい雰囲気
今回は行けないオーベルニュ

https://goo.gl/maps/DoWfyKBoTZL2
Abbatiale Saint-Austremoine - Issoire「迷える羊を救うクリスト」
※ゴール的な諧謔と哄笑を想起させる(p123)
「教会堂には400を超える柱頭彫刻があり、そのうち188が内部を飾っています。大半は植物モティーフやギリシアのコリント式柱頭からインスパイアされたものですが、ローマからインスパイアされたものも見られます。」http://www.balade-roman.com/


サン=ネクテール (Saint-Nectaire)
https://www.france-voyage.com/


ル・ピュイ=アン=ヴレ (Le Puy-en-Velay)
Cathédrale Notre-Dame-du-Puy
https://4travel.jp/
http://fishand.tips/


クレルモン・フェラン
Clermont-Ferrand cathedral(この地方の石は火山性で黒い)
フランスロマネスク→の旅計画2019に戻る