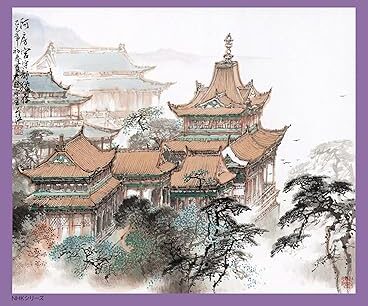中国 古都の詩(うた): 華北編
NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ
– 2025/3/24 赤井 益久 (著)
詩に綴られた、いにしえの都市を生きた人たちの暮らしと想い。悠久の歴史を持つ中国は、天下が統一され、主だった王朝だけでも秦・漢・三国・南北朝・隋・唐・宋・元・明・清を数える。その間には五代十六国や、北方の異民族国家と併存する時代もあった。そのいずれもが、都を定め、国家運営の中心として意識された。首都や副都、それに準じる都市は、歴史上重要であるばかりでなく、詩人たちには時に自らの故郷として意識され、精神的なより所として大きな部分を占めた。
「漢詩をよむ」2025年度は、「古都の詩(うた)」と題して、歴代の都と、それに準じる都市を詠じた漢詩を取り上げる。前期は華北の都市で詠まれた詩を味わう。
2023年放送大学の科目は「中国と東部ユーラシアの歴史」だった・・都市から見る中国という感じもあったのだが・・。
中国を旅しようと考えていますが、中国は広いですね。
ヨーロッパに比べて、近いので、何回かに分けていこうかと思ったばかりです・・
○咸陽 許渾「咸陽城東楼」(七律) 李商隠「咸陽」(七絶)など
○長安(1) 儲光羲「長安道」(五絶) 章八元「題慈恩塔」(七律)など
○長安(2) 韓偓「重遊曲江」(七絶)など
○洛陽(1) 杜牧「洛陽秋夕」(七絶) 許渾「登故洛陽城」(七律)など
○洛陽(2) 顧況「洛陽早春」(五律) 張籍「秋思」(七絶)など
○太原 李白「太原早秋」(五律) 蘇頲「汾上驚秋」(五絶)など
○成都 鄭谷「蜀中」(七律) 雍陶「経杜甫旧宅」(七律)など
○大都 高適「自薊北帰」(五律) 張説「幽州新歳作」(七律)など
咸陽城東の樓 許渾
一たび高城に上れば 萬里愁う
蒹葭楊柳 汀洲に似たり
溪雲初めて起こって 日閣に沈み
山雨來らんと欲して 風樓に滿つ
鳥は綠蕪に下る 秦苑の夕べ
蝉は黄葉に鳴く 漢宮の秋
行人問うこと莫れ 當年の事
故國東來 渭水流る
故事成語
「山雨来たらんと欲して風楼に満つ」
許渾の「咸陽城東楼詩」の「渓雲初起日沈閣、山雨欲来風満楼」から。山雨が降り出そうとする前にまず風が高楼に吹きつけてくる。転じて、今にも大事件が起こりそうな、穏やかでない雰囲気が立ちこめている状態のたとえ。
当時は唐王朝の衰退期にあたり、将来を心配する気持ちの現れと見られている。
読みと解説 shigin.com/ 咸陽市(かんよう-し)は中華人民共和国陝西省に位置する地級市。秦朝の首都
重遊曲江 韓偓
鞭梢乱払暗傷情
蹤跡難尋露草青
猶是玉輪曾輾処
一泓秋水漲浮萍
重ねて曲江に遊ぶ
鞭梢(べんしょう)乱れ払い 暗(あん)に情(じょう)を傷む
蹤跡(しょうせき)尋ね難く 露草(ろそう)青し
猶(な)お是(こ)れ玉輪の曾(かつ)て輾(ひ)きし処(ところ)
一泓(いっこう)の秋水(しゅうすい) 浮萍(ふひょう)を漲(みなぎ)ら
漢詩の歳時記 秋冬編
NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ – 2024/9/26赤井 益久 (著)
漢詩をよむ」は重厚な朗読とわかりやすい解説で漢詩に親しんでいただこうと、1985年から始まった長寿番組。私たちに馴染みのある詩人たちの漢詩を取り上げ、小学生から九十代に至るまで幅広い年齢層の方々から反響を頂いてきた。
「漢詩をよむ」2024年度は、漢詩における「歳時記」がテーマ。「歳時記」は日本では江戸時代以降の主に俳句の季語を分類したものを指すが、本来は、四季に応じた事物や行事などを列挙した中国古来のもの。
前期は、白居易、李白、蘇軾、韓愈といった詩人たちが、生活を彩る風俗習慣を季節ごとに巧みに取り入れ表現した詩の数々を紹介する。
講師は中国唐代詩研究の第一人者で、精緻でわかりやすい解説に定評がある國學院大学名誉教授・赤井益久さん。
冬枯れから芽吹きへ。夜長や風雪を愁い、春を待望する想いが込められた名作を味わう
穏やかな朗読とわかりやすい解説で漢詩の魅力を紹介する「漢詩をよむ」。後期のテキストでは、漢詩における「歳時記」をテーマに、名作を紹介・鑑賞する。
「漢詩をよむ」2024年度10月から翌年3月までの後期では、秋から冬へと季節が移ろうなか、自然の変化や人びとの営み、節句や祭りに材を取り、哀感や郷愁、春を待つ想いがこめられた作品を鑑賞する。秋の夜長、虫の声、初霜や初雪、冬衣、冬至、大晦日、元旦、人日(正月七日)、小元(正月十五日)、元宵(同日夜)、寒食(冬至から百五日目)、柳絮……といったそれぞれの題材を、李白、白居易、蘇轍、韋応物、王維、杜牧、陸游といった詩人たちが描いた秀作を、存分に味わう。
漢詩の歳時記 春夏編
<4月~9月>「漢詩の歳時記~春夏編」(変更になる場合があります)
*四月「春寒」「春雲」「流鶯」。韓愈「晩春」、王安石「南浦」他*五月「五月」「立夏」「端午」。真山民「初夏」、陸游「五月初作」*六月「夏至」「暑雨」「大水」。蘇軾「六月二十七日望湖楼酔書五絶」、趙翼「毒暑」。七月「七夕」「納涼」「扇」など。李白「夏日山中」、白居易「香山避暑」*八月「秋風」「中秋」「月光」。李白「静夜思」、翁巻「中秋歩月」他*九月「白露」「秋暮」「秋雁」な。駱賓王「秋雁」、銭起「九日田舎」など。
人生をたたえる詩
NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ 人生をたたえる詩: 詩人たちはいかに生きたか – 2023/3/25
封建社会の中国では家柄によって身分が定まり、仕官しても政治闘争や派閥争いなどにより、詩人たちの運命は翻弄され自由な発言や行動ができない状況にあった。この時代の詩人たちは、そのような世の中を疎み社会から遠ざかる自由な生き方に憧れを抱くようになり、一見姑息に見えるこの処世法が詩人たちの理想になっていく。
2023年度の前半・4-9月は、隠棲生活の中から前向きに生きる喜びを詠った名詩の数々を紹介する。
李白「春日、酔いより起きて志を言う」、
孟浩然「洛より越に之く」、
杜甫「貧交行」ほか。逆境にあっても前向きな姿を貫いた詩人たちの生きかた
詩人が愛した花の世界: 秋冬編
NHKカルチャーラジオ 漢詩をよむ(NHKシリーズ)
赤井 益久 | 2022/9/24
秋冬の植物の姿、そこに託した自らの心中や境遇を詠んだ名品を味わう。
「漢詩をよむ」2022年度秋冬 秋が深まると木々が色づき、人びとのこころにも寂しさが去来する。冬になれば野原は荒涼とし、雪が木々を装うのを見て、ひとは春の訪れを渇望する–。
杜甫や王維をはじめ、杜牧、白居易、韋応物、陶淵明といった名だたる詩人が、秋冬の植物に材を取り、望郷の念やひとの心の移り変わりを詠んだ味わい深い漢詩の名作を、語注や現代語訳も掲げて丁寧に解説する。
地球の歩き方(北京)
地球の歩き方の新刊 (2025~2026)は、まだ、北京しか出ていない( 2024/11/14)https://amzn.to/3RgMPuO
まず北京でしょうね‥
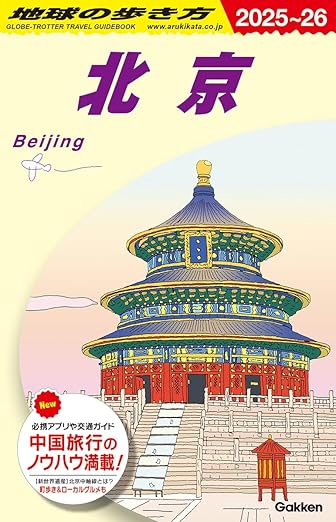
便利な地下鉄に乗って気軽に行ける水郷古鎮をはじめ、美食に雑技にお買い物、人気の見どころや最新注目スポットも総まくり。上海、蘇州、杭州に加え、足を延ばして南京、無錫を訪れるときにも必携の一冊